「自分の強みを活かす」ことは、キャリアや人間関係を前進させる上で欠かせない考え方です。ですが、その“強み”が、時に人を傷つけたり、自分自身を追い込んでしまう場面を目にしたことはありませんか?
実は、強みと弱みは表裏一体。どんなに優れた特性であっても、心の状態や状況によっては“裏目に出る”ことがあるのです。そしてそれを左右するのが、「自分の心をどう扱うか」という“内なるスキル”——心理的資本と呼ばれる、ポジティブな心の力です。
本記事では、強みがなぜ時に足を引っ張るのか。そして、どうすれば本来の輝きを取り戻せるのか。具体的な事例を交えながら、そのヒントをお届けします。
読み終えたとき、「強みを知る」だけでは足りなかったことに気づくはずです。いえ、気づいていただけると嬉しいです。
Contents
強みと弱みはコインの裏表
「自分の強みを活かしましょう」という言葉は、自己分析やキャリア開発の場で頻繁に聞かれます。もちろん、これは間違っていません。ただ、ここにはひとつ大きな落とし穴があります。
強みは、状況や心の状態次第で「弱み」にもなり得るということ。そして、その強みが強みとして発揮されるか否かは、本人の心理的資本(心の状態とそれをマネジメントする力)に深く依存しているのです。
事例:論理的思考がチームを疲弊させるとき

たとえば、Aさん(30代・男性・プロジェクトマネージャー)は「論理的思考」が強みだと自負しています。複雑な問題を構造化し、原因を特定し、論理的に解決策を導く力は、確かにプロジェクト推進の要です。
しかし、あるとき部下からこんなフィードバックがありました。
Aさんは、部下の感情や背景に寄り添う余裕がない状態に陥っていたのです。締切のプレッシャーや、自身の「失敗できない」という思い込みが募るにつれ、“論理的思考”は“冷たい批判”として表れてしまっていたのです。
その強みが“輝くとき”と“裏目に出るとき”の違い
同じ「論理的思考」という特性でも、それがプラスに働くかマイナスに働くかは以下のような心の状態によって左右されます。
| 心の状態が整っているとき | 心が疲弊しているとき |
|---|---|
| 解決志向で、相手の話に耳を傾けながら提案できる | 自分の意見を押し通し、批判的な態度になってしまう |
| 論点整理によって全体を助ける | 細かい揚げ足取りに終始してしまう |
この違いを生むのが、心理的資本(希望、自己効力感、レジリエンス、楽観)と呼ばれる「心の筋力」です。
強みを知るだけでは片手落ち
自己分析で自分の強みを知ることは重要ですが、それだけでは不十分です。
- どんな状況のときに、自分の強みが裏目に出るのか?
- 心がどんな状態だと、強みがネガティブに表れるのか?
- どうすれば、自分をフラットに戻せるのか?
こうした問いと向き合うことで、初めて「強みを活かすとはどういうことか」を理解できるようになります。
心の状態を整える「内なるコントロール力」
Aさんのケースでは、心理的資本を意識するようになってから、少しずつ変化が起こりました。深呼吸の習慣、週1回の「自分を褒める時間」、そして信頼できる同僚とのミニ相談タイム。
これらは心理的資本を開発したりコントロールするための手段のほんの一部に過ぎませんが、それだけで、余裕のあるときのAさんは、以前のような「冷たい論理」ではなく、「安心感のある構造化アドバイス」を提供できるようになったのです。
まとめ
強みは、心の状態によって「刃」にも「光」にもなります。だからこそ大切なのは、
- 自分の特性(強み)を知ること
- その特性が“裏目に出る時”を理解すること
- 心を整える力=心理的資本を高めること
これらをセットで考え、実践することだと思います。
自分の“強み”を本当に活かしたいなら、実は「心の状態を整える力」こそが最重要の土台になるのです。でなければ、弱みとして表出してしまいますから。
心理的資本の概念を学び、開発法や制御法となるガイディング(心理的資本を開発する思考法や手法)を学びたい方は、ぜひPsyCapMaster®認定講座の受講をご検討くださいね。

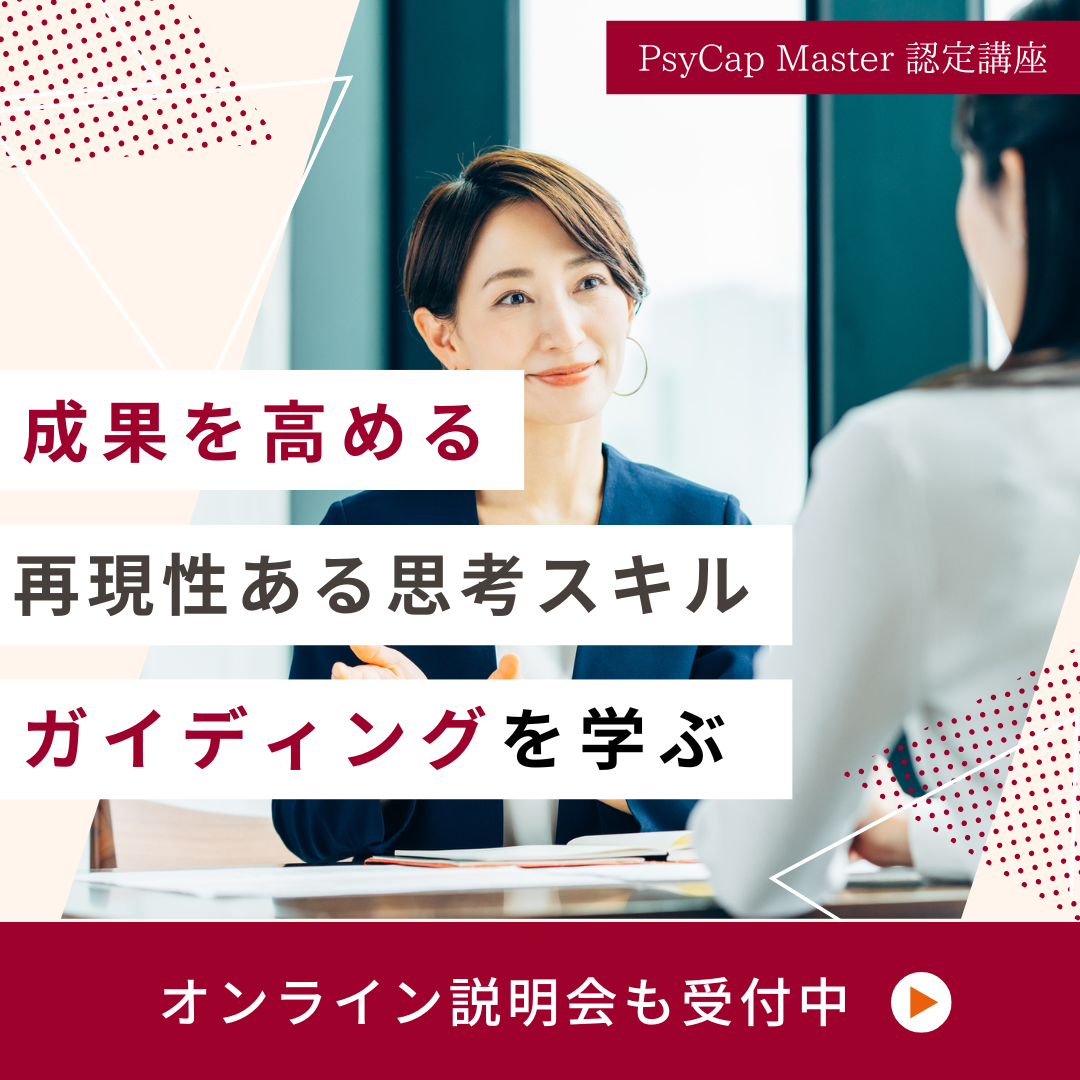

コメント