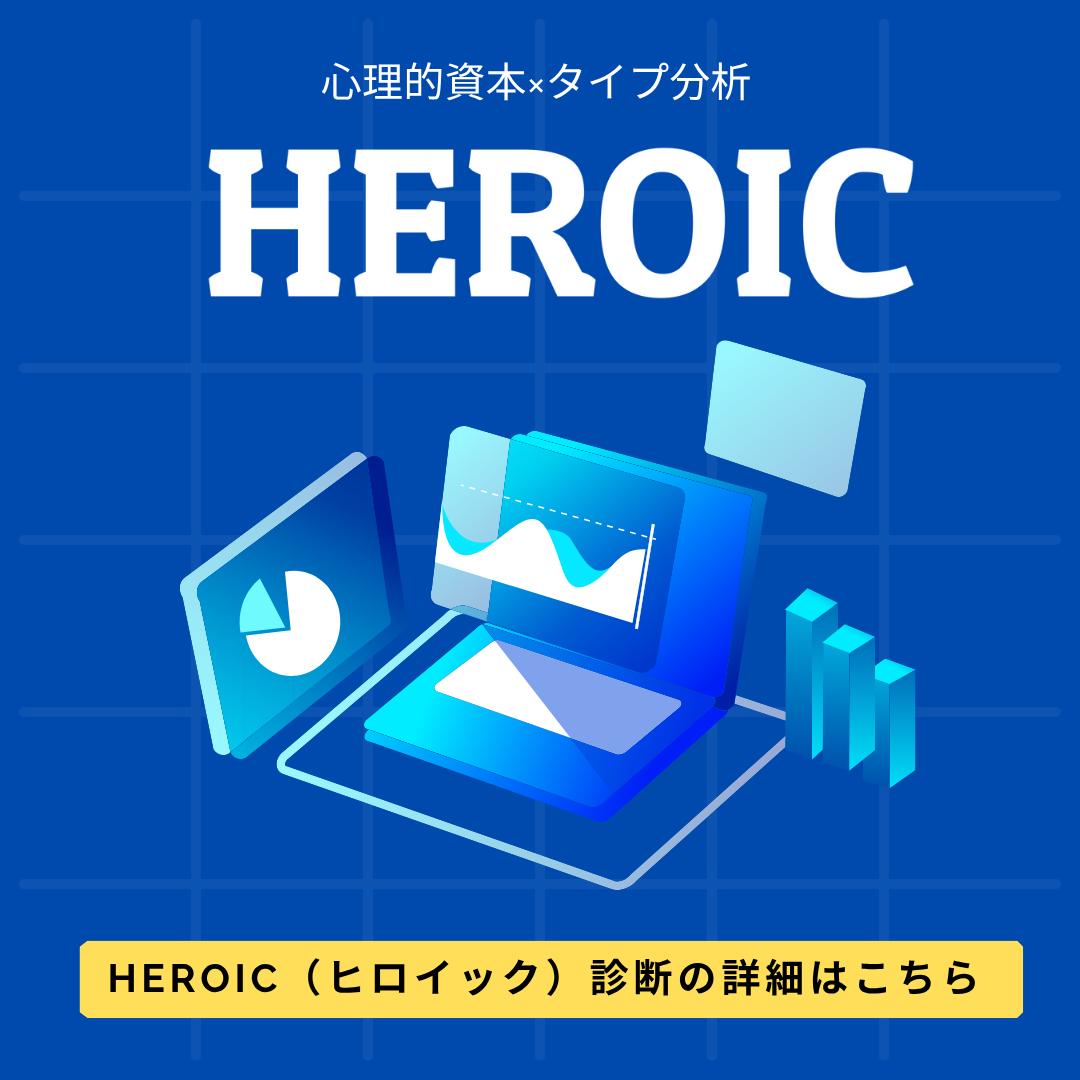「子どもが風邪をひくのは、親がちゃんとしていないからだ」
そう言われ、私は仕事を失ったことがある。
当時、私は3歳の長男と1歳になったばかりの長女を保育園に預け、フルタイムで仕事を再開し始めたばかり。
経験した方ならわかると思うが、保育園に通い始めたばかりの子どもは、ありとあらゆる病気をもらってくるまさに「洗礼」と呼ばれる時期を迎えており、確かに突如のシフト交代や、早退をすることも多かったのは事実。
そんな中言われた、上司からの一言だった。
この経験はもう20年ほど前のことだが、この出来事を振り返るたびに、日本社会には「強くあらねばならない」という空気が根強く残っているということ。そして、それは20年経った今も変わらず心のどこかに存在し、親に限らず、社会全体に「強さ」に対するプレッシャーがあるのではないかということだ。
「親がすべての責任を負うべき」という価値観
日本では昔から、「忍耐」や「努力」が美徳とされてきた影響なのか、「男は泣くな」「女性は耐えるもの」なんていう固定観念や、「仕事は休むな」「風邪は甘え」なんていう考え方もよく耳にする。。そうした価値観は、親に対しても同じように押しつけられがちだ。
「子どもの健康管理は親の責任」「親がしっかりしていれば、子どもは風邪をひかない」そんな極端な意見が、親に「完璧であること」を求めるプレッシャーになっている気がする。
現代社会は、少しずつ変わってきているとはいえ、20年経った今もこの価値観の根本は変わっていないのではないだろうか。
「強くあらねばならない」という呪い
「子どもが風邪を引くのは親のせいだ」
この言葉を言われたとき、私は「そんなわけないでしょう」と反発する一方で、他人に言われたことで「もしかして私が悪いのかも……」と、まるで呪いにかけられたような気分になりました。
同じような経験をしている親は、きっと多いはず。たった一言でも、「自分がもっと頑張らないと」と追い詰められてしまうのだ。
さらに、「完璧な親でなければならない」というプレッシャーは、親だけでなく子どもにも影響を与える。親が「ちゃんとしなきゃ」と思うあまり、無意識のうちに子どもにも厳しいルールを押しつけてしまうことはないだろうか。
そしてそのような価値観で育ってしまう子どもたちにも、「強くあらねばならない」という思いが潜在的に存在してしまうことで、20年経った今の時代も根本的な部分は変わっていないのかも知れない。
「頼ること」もまた強さ
「強い人」と聞くと、「何でも自分で解決できる人」を思い浮かべるかもしれない。でも、それは本当に「強さ」といえるのだろうか。
本当に強い人とは、「自分の限界を知って、必要なときに周りに助けを求められる人」ではないか。
無理なことを無理と素直に言えること。 「助けて」と声を上げること。
そして何より、誰かを頼ることで、自分はもちろんラクになれるし、相手もまた頼りやすくなるという好循環が生まれる。「持続可能な社会」と最近はよく耳にするが、持続させるのなら、「互いに支え合うこと」は非常に意味があり、またどんな立場にいる人たちも生きやすく、そして社会も今よりずっと良くなるのではないかと思う。
さいごに
私たちは、本当に「強く」ある必要があるのか?
そんな疑問に答えを提示してくれるのがこちらの動画。
この動画では「強くあらねばらないという呪い」へ立ち向かうための「術」と「本当の強さ」について簡単に解説しています。このコラムに共感した!という方はぜひご覧ください!