「ワークライフバランス」という言葉は、仕事と私生活を「天秤にかける」ようなイメージを持たれがちですが、その実態はもっと複雑で個人的なものです。理想的な50:50の比率を取ろうと試みても、現実には仕事の繁忙期やライフイベントによって、その割合は常に変動します。
私たちが本当に目指すべきは、単純な「バランス」ではなく、お互いが補完し合い、高め合う「調和(ハーモニー)」にあるのではないでしょうか。
Contents
バランスの困難さ—そして「インテグレーション」という視点
多くの方が実感されている通り、ワークとライフのバランスを取るのは容易ではありません。
- ワークがライフを支える時: 生計を立てるために仕事に打ち込むことは、充実した私生活を送るための基盤となります。時には、がむしゃらに働かなければ、家族の生活や将来設計が立ち行かない、という状況もあるでしょう。
- ライフがワークを規定する時: 育児や介護、あるいは体調管理など、私生活の責任や制約が、仕事に割ける時間やエネルギーを制限することもあります。「もっと働きたい」という意欲があっても、叶わない状況も存在します。
冒頭で触れた、知人からの「ワークライフインテグレーション(統合)」という指摘は、まさにこの複雑な関係を言い表しています。インテグレーションとは、ワークとライフがごちゃ混ぜで、どちらか一方を切り離して語れない状態です。これは、やらされ仕事ではなく、自分の意思と情熱をもって取り組んでいるからこそ成立します。仕事が人生の一部であり、生活の質が仕事のパフォーマンスを左右する、という相乗効果を生む状態です。
「最適解」は誰にも決められない主観の世界
多くの議論や制度設計は、とかく客観的な指標や一律の基準を設けようとします。しかし、何をもって「バランスが取れている」とするかは、完全に主観の世界です。
- ある人にとっての理想は、「仕事に没頭し、趣味や休息は極力抑える」という高い仕事比重かもしれません。
- 別のある人にとっての最適解は、「家族との時間を最優先し、仕事は定時で切り上げる」という高い生活比重かもしれません。
この「最適解」は、年齢、キャリアの段階、家族構成、健康状態によって絶えず変化するものです。だからこそ、他者が勝手に個人の状況を「バランスが悪い」と断じたり、過度に干渉することは避けるべきです。本人が納得し、充実感を得ていれば、それがその時点でのベストな調和なのです。
それでも必要な「周囲の目」と「ウェルビーイング」
個人の意思を尊重すべきとはいえ、唯一の例外は、本人が不健康な状態に陥っている時です。夢中になりすぎたり、義務感に囚われたりすると、人は知らず知らずのうちに心身の限界を超えてしまうことがあります。
この点で、「ウェルビーイング(Well-being:身体的、精神的、社会的に良好な状態)」の概念は、ワークライフの議論と深く結びつきます。
ウェルビーイングな状態を維持するために重要なこと:
- 気づきと自己認識: 自分が今、疲弊していないか、過度なストレスを抱えていないか、立ち止まって振り返る習慣を持つこと。
- 周囲のサポート: 家族や同僚が、異変に気づいた際に、「休むこと」を恐れず進言し、サポートできる環境と文化があること。
- 権利としての休息: 休息や活動が「わがまま」ではなく、生産性や創造性を高めるための権利であり、必要な投資であるという共通認識を持つこと。
すべての活動への感謝
より働きたい、もっと活動したいというポジティブな意欲があるにもかかわらず、それが叶わない状況は、ストレスやフラストレーションとなって蓄積しやすいものです。人間は、思うようにいかないことに直面すると、どうしても弱い一面を見せてしまいます。
この考察を通じて、改めて痛感するのは、私たちが働くことができる、遊べる、そして安心して休むことができる、すべての活動は決して当たり前ではないということです。
この恵まれた環境は、誰かの努力、社会のインフラ、そして協力し合う人々の「がんばり」があってこそ成り立っています。この事実に心から感謝し、私たち一人ひとりが、自分にとっての最高の調和を見つけ、豊かな人生を歩んでいけるよう努めていきたいものです。

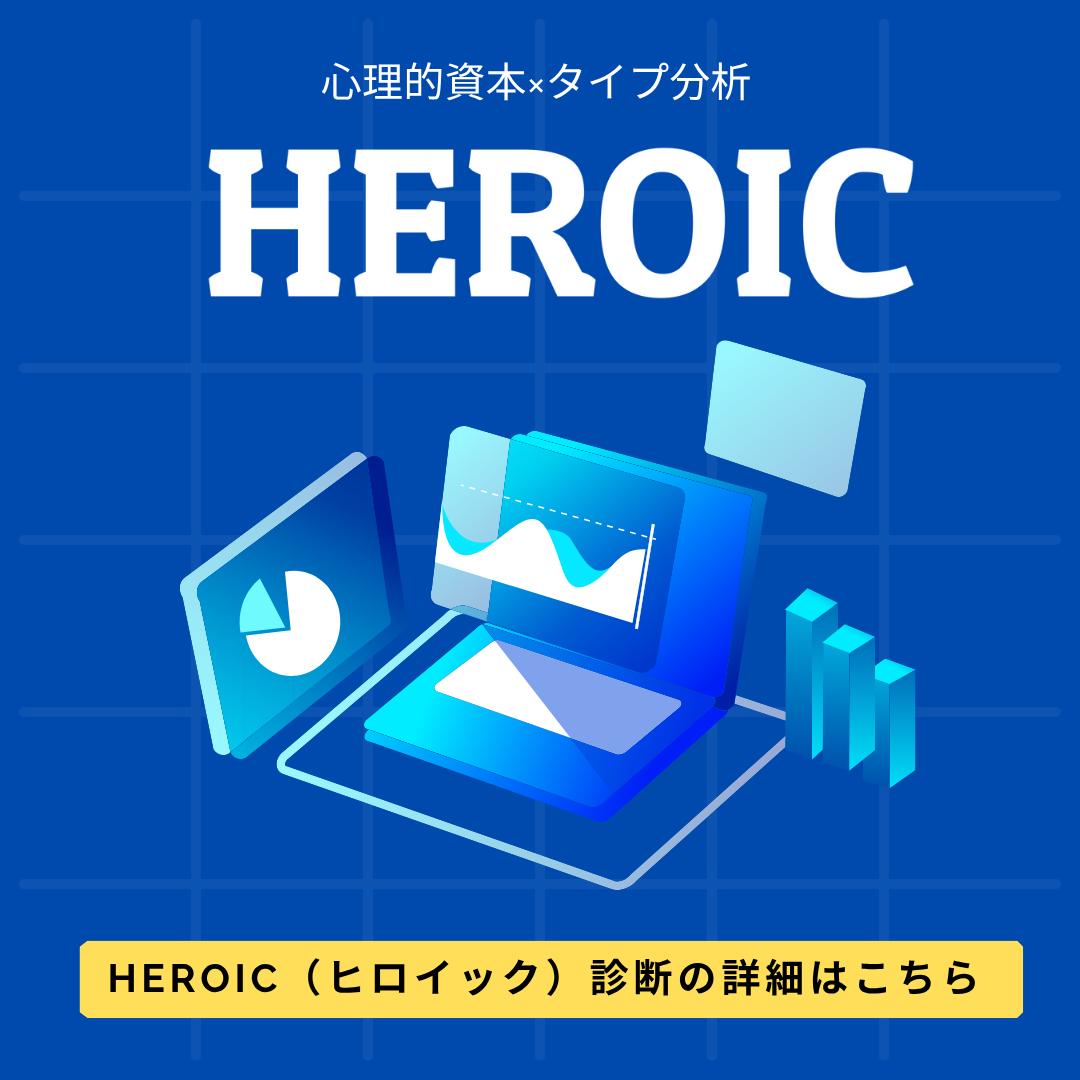

コメント