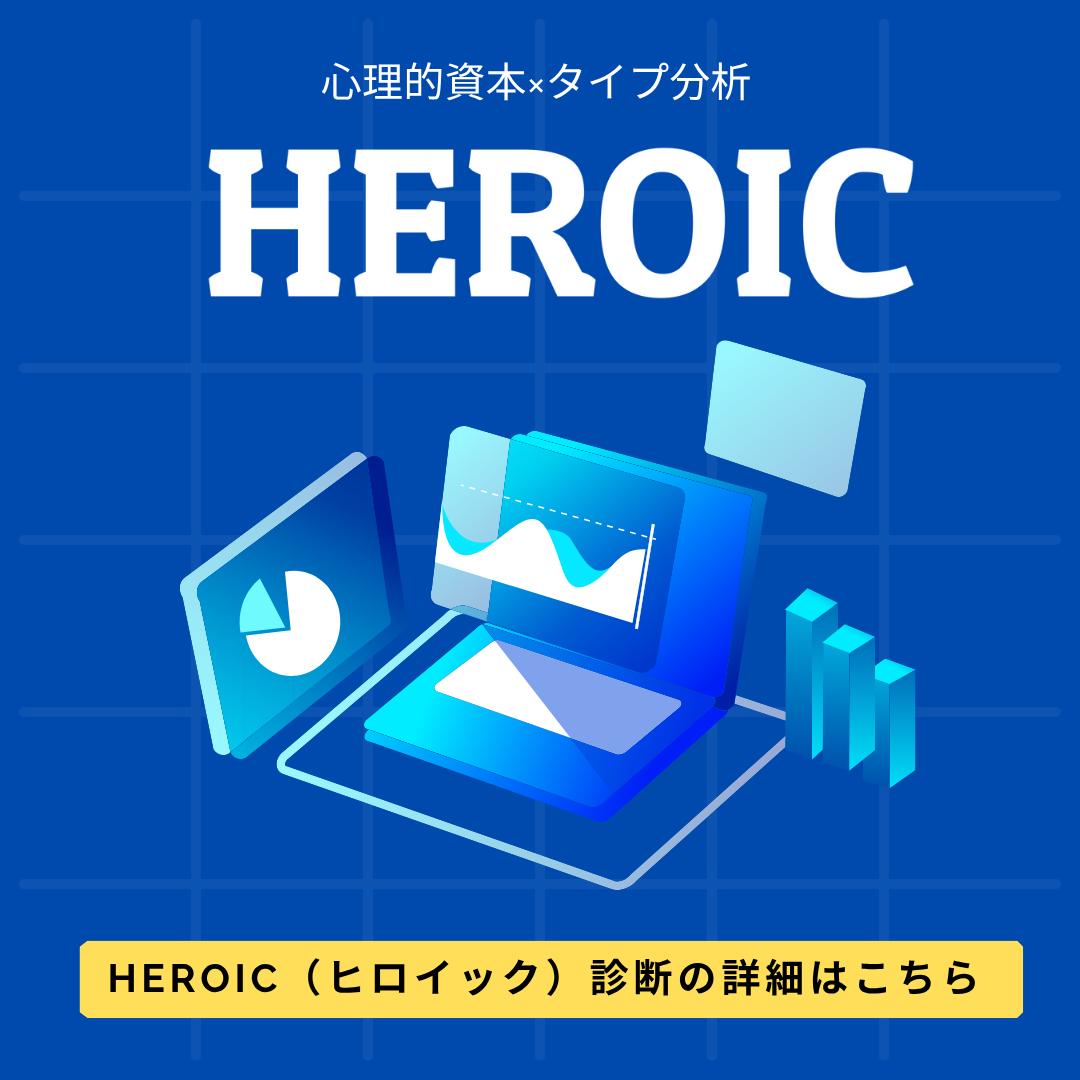「うちのチーム、個々の能力は高いはずなのに、なぜかうまく噛み合わない…」
「またあの人と同じことで揉めてしまった…」
「会議で話は盛り上がるのに、一向にプロジェクトが進まない…」
チームで働く中で、こんな風に感じた経験はありませんか? 多くの人が、チームのパフォーマンスを最大限に引き出すことの難しさを感じています。そして、その原因を「個人のスキル不足」や、もっと漠然と「相性の問題」で片付けてしまいがちです。
本コラムでは「チームの力」について、少しだけ深く、そして正直に考えてみたいと思います。日々の仕事の中で皆さんが感じている「もどかしさ」の正体を、一緒に探るような感覚で目を通していただければ嬉しいです。
Contents
■ 足を引っ張っているのは「スキル」よりも「見えない何か」
チームの力が発揮されない時、つい「誰の知識が足りないか」「何のスキルが不足しているか」といった、目に見えやすい部分に原因を求めがちです。もちろん、それらも大切な要素です。
しかし、皆さんも感じておられると思うのですが、チームの足を引っ張っているのは、コミュニケーションの問題であることが多いのです。
例えば、専門知識が豊富なAさんと、高い技術力を持つBさんがいるとします。この二人が協力すれば素晴らしい成果が生まれそうなのに、なぜかいつも意見が対立し、仕事がスムーズに進まない。これは、AさんやBさんの「知識」や「スキル」に問題があるのでしょうか? おそらく、そうではありません。
問題の根源は、もっと内面的な部分、つまり一人ひとりの行動や思考の「クセ」のようなものに隠されています。
知識やスキルの強み・弱みは、比較的わかりやすいですよね。「〇〇さんは会計に詳しい」「△△さんはプログラミングが苦手だ」といったことは、周囲からも見えやすく、評価もしやすい。しかし、コミュニケーションの裏側にある、個々の行動や思考における強み・弱みは、非常に分かりにくいのです。
なぜなら、私たちは誰でも、無意識のうちに「自分のフィルター」を通して相手を見てしまうからです。そこには当然、バイアス(思い込みや偏見)がかかります。さらに厄介なのは、本人でさえ自分の行動や思考のクセを自覚できていないことが多い、という点です。
「あの人は、どうしていつも細かいことばかり気にするんだろう?」
「なぜ、この人はすぐに『やろう!』と飛びつくんだろう?もっと慎重に考えるべきなのに」
こんな風に感じた時、私たちは相手の「弱み」を見ているつもりかもしれません。でも、それは本当に「弱み」なのでしょうか。そして、この手の話を本人に直接伝えるのは、とても勇気がいりますよね。「あなたはこういうタイプだから」と指摘することは、相手を決めつけるような響きがあり、非常に繊細なテーマだからです。
だからこそ、私たちは一度立ち止まって、客観的な視点を取り入れる必要があるのかもしれません。
■ 「自分を知る」ことから始まる、新しいチームの関係性
そこで、世の中に数多く存在する「タイプ診断」のようなツールが、思いのほか大きな力を発揮します。
「なんだ、また性格診断か」と思われるかもしれません。しかし、ここでの目的は「あなたは〇〇タイプです」とレッテルを貼ることではありません。客観的な指標をコンパスのように使い、まずは「自分自身を理解する」こと、そして次に「自分とは違う他者を理解する」こと。そのために、こうしたツールは使いようによっては、効果的なのです。
チームビルディングや組織開発というと、「メンバーの強みを活かして、適材適所で最高のパフォーマンスを!」といった、理想が語られがちです。もちろん、それは素晴らしい理想です。
しかし、現実の職場を思い浮かべてみてください。すべてのポジションに最適な人材がいるでしょうか? いつも自分の得意な仕事ばかりできるでしょうか? 多くの場合は、限られたメンバーで、得意なことも苦手なことも含めて、なんとか協力して成果を出さなくてはなりません。
そう考えた時、「強み」ばかりに注目していると、チームにとって非常に大切な視点が抜け落ちてしまいます。それは、チームの「弱み」や「課題」とどう向き合うか、という視点です。
きれいごとで終わらないチームづくりは、むしろ、この「弱み」と向き合うところから始まると言っても過言ではないかもしれません。
■ 本当の意味でチーム力を上げるための3つのステップ
では、具体的にどうすれば「弱み」と向き合い、それを力に変えることができるのでしょうか。私は、次の3つのステップが基本になってくると考えています。
ステップ①:自己理解 ― 自分の「光と影」を知る
まずは、自分自身のことからです。自分の行動や思考のタイプを知り、それが「強み」としてどう現れるかを理解することは大切です。しかし、それと同じくらい重要なのが、その特性が「弱み」として、つまり良くない方向に発揮されると、周囲からどう見えるのかを知っておくことです。
例えば、新しいアイデアを次々と思いつき、行動に移すのが得意なタイプがいるとします。これは素晴らしい「強み」です。しかし、そのエネルギーが裏目に出ると、「計画性がない」「飽きっぽい」「言っていることがコロコロ変わる」と見えてしまうかもしれません。
逆に、一つのことをじっくりと考え、石橋を叩いて渡る慎重なタイプ。これもまた、ミスのない確実な仕事をする上で欠かせない「強み」です。しかし、時には「行動が遅い」「決断力がない」「理屈ばかりで動かない」という「弱み」として映る可能性もあります。
大切なのは、自分の特性には「光」の側面と「影」の側面がある、と自覚することです。良い・悪いではなく、そういう傾向を持っていると知る。それが、チーム内でのすれ違いを減らす第一歩になります。
ステップ②:他者理解 ― 「違い」を尊重し、受け入れる
次に、他のチームメンバーに目を向けます。もちろん、メンバーにもそれぞれのタイプがあり、それぞれの「光と影」があります。
ここで絶対に避けたいのは、「あの人は〇〇タイプだから」という決めつけです。そうではなく、「自分とは物事の捉え方や進め方が違うタイプなんだな」と、まずはその「違い」を事実として受け入れること。これが、本当の意味での協働の始まりです。
自分とは違う他者の行動や思考の背景を想像してみる。すると、これまで理解できなかった相手の言動が、単なる「嫌な部分」ではなく、その人の「特性」として見えてくることがあります。
ステップ③:関係性とチームを理解する ― 「私たち」の化学反応を知る
個人を理解できたら、最後はチーム全体です。メンバーのタイプの組み合わせによって、チームには独特の「化学反応」が生まれます。
タイプの組み合わせに絶対的な正解はありません。しかし、相性は確かに存在します。例えば、あまり細かい前提を擦り合わせなくても、なぜかスムーズに仕事が進む組み合わせ。逆に、一つひとつ丁寧にコミュニケーションを取らないと、すぐに行き違いが起こる組み合わせ。そして、強みと弱みがパズルのピースのように噛み合い、うまく機能すれば「スピード」と「質」を両立できる、強い補完関係が生まれる組み合わせ。
自分たちのチームが、どのようなタイプのメンバーで構成されていて、どのような化学反応が起きやすいのか。それを客観的に把握することで、チーム運営の舵取りが格段にしやすくなります。
■ 「なんで?」が「なるほど!」に変わる瞬間
「なんでこの人は、この前と言ってることが全然違うんだろう?」
「どうして、うちのチームは議論ばかりして一向に物事が決まらないんだろう?」
日常業務でふと湧き上がる、こんな疑問や不満。これを、単に「あの人とは合わないな」「このチームは自分に合ってないかも」と、少しネガティブな感情で片付けてしまうのは、非常にもったいないことです。
ここで、「タイプの視点」を取り入れてみましょう。すると、今までとは全く違う景色が見えてくるはずです。
コロコロと意見が変わるように見えた同僚は、実は感性が豊かで、次から次へと新しいアイデアが湧いてくるタイプなのかもしれません。自分が一つのことを着実に進めたいタイプだからこそ、その変化が「一貫性のなさ」に見えていただけかもしれないのです。
議論ばかりで進まないチームは、もしかすると慎重に多角的な視点から物事を検討してから動きたいタイプが多いのかもしれません。「まずやってみよう!」と考える自分から見ると、それが「停滞」に感じられるだけかもしれないのです。
このように、タイプの視点は、感情的になりがちな状況を客観的に捉え直すきっかけを与えてくれます。
個人レベルではどうでしょうか。例えば、自分が「アイデアを出すのは得意だけど、それを着実に実行するのは苦手だな」と自覚しているとします。さらに、「もしかしたら、チームメンバーからは『また違うことを言っている』『飽きっぽい』と思われている可能性もあるな」と想像できれば、コミュニケーションのすれ違いが起きた時に、その原因を相手だけに求めるのではなく、自分自身にも問いかけることができるようになります。
「あ、また自分のクセが出てしまったかも。今のアイデアは一旦置いておいて、まずは決まったことを進めるための具体的な話をしよう」と、自分の行動を修正できるのです。
チームレベルでも同じです。「このチームは、じっくり考えて着実に動くのが得意。一方で、議論が長引き、動き出しが遅くなりがちという弱みがある」という共通認識をチーム全体で持てていたらどうでしょう。実際に会議が長引き、停滞感が出てきた時に、誰かが「そろそろ動きながら考えた方が、新しい発見があるかもしれませんね」と軌道修正の一言を投げかけることができます。
これは、「チーム力が高い状態」の一つの現われではないでしょうか。問題が起きた時に、誰か一人が悪いと犯人探しをするのではなく、チーム全体の傾向として捉え、みんなで乗り越えようとする。そんなしなやかさが生まれます。
■ 「弱さ」を受け入れる強さと、心理的資本
ただし、自分や他者の「弱み」と向き合い、それを受け入れるには、精神的なエネルギーが必要です。異なるタイプの意見を受け入れる「器の大きさ」が求められます。
この器の大きさは、個人の「自信」と、変化に対して柔軟に対応できる「適応力」に支えられています。私たちは、このような「心のエネルギー」を『心理的資本』と呼んでいます。心理的資本が高い状態にあれば、他者からのフィードバックを前向きに受け止めたり、チームの方針転換にも柔軟に対応したりすることができます。弱みと向き合うことは、時として痛みを伴いますが、その痛みを乗り越えるための土台となるのが、この心理的資本なのです。
■ まとめ:理想だけでは、チームは前に進めない
チーム力を高めるプロセスは、理想を語るだけでは始まりません。むしろ、自分たちの不完全さやうまくいかない部分、つまり「弱み」から目をそらさず、現実的な課題として向き合うことから始まります。
「弱み」と向き合うことは、チームの可能性を狭めることではありません。むしろ、課題を乗り越えるための具体的なヒントを与えてくれます。自分たちの「影」の部分を知ることで、初めて「光」の部分を最大限に活かす方法が見えてくるのです。
それは、メンバー一人ひとりが安心して自分の弱さを開示でき、お互いの違いを補い合える、本当に強いチームへの第一歩となるはずです。
私たちBe&Doが提供するHEROIC診断は、この記事でお話しした『心理的資本』と『行動・思考のタイプ』の両面から、個人と組織の状態を可視化するツールです。きれいごとではない、現実的なチームづくりの一歩を、データという客観的な視点からサポートします。ご興味があれば、ぜひ一度お声がけください。