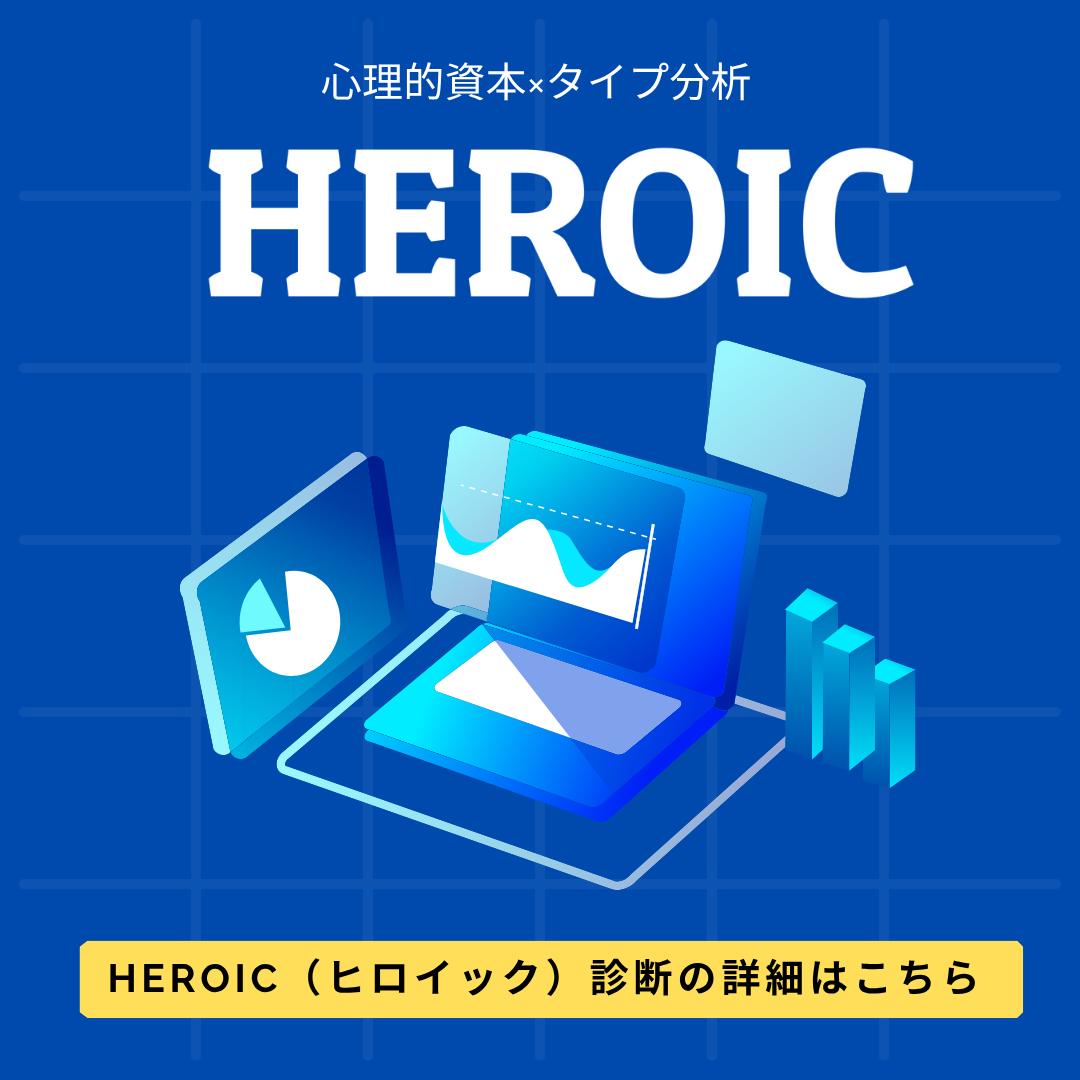先日、ある企業のコンサルティングで、深く考えさせられる場面に出会いました。 ひとりは、どこか諦めた表情でこう語る中堅社員のAさん。 「うちの職場は、結局のところ上の言うことが絶対ですから。何か言っても変わらないんです」
そしてもうひとりは、Aさんの上司である管理職のBさん。私にこう胸の内を明かします。

「最近のメンバーは、会議で意見を求めても何も出てこなくて。一体、やる気はあるんでしょうかね…?」
この、あまりにも両義的な状況。メンバーから見れば「言っても無駄な職場」、管理職から見れば「意見を言わない部下たち」。両者の間には、深い溝が・・・。
この問題を、単に「心理的安全性が低い」という言葉で片付けてしまうのは、本質を見誤るかもしれません。これは手法の問題というより、長年かけて醸成された、組織の根深い風土そのものの問題です。
Contents
なぜ「場のルール」だけでは変われないのか
こうした状況を打破しようと、多くの企業が「会議では役職関係なく発言しよう」「反対意見を歓迎します」といったルールを設けます。しかし残念ながら、その多くは掛け声だけで終わってしまいます。
なぜなら、いくら立派なルールを作っても、議論を受け止める側と、意見を表明する側の双方に、それを受け止め、実行するだけの心の土台ができていなければ、何も機能しないからです。
では、その心の土台とは一体何でしょうか。 それは「健全な自信」、つまり、充実した「心理的資本」ではないでしょうか。そして、それは管理職とメンバー、その双方に異なる形で求められるのです。
管理職に問われる「異論を受け止める自信」
管理職であるBさんは、本心からメンバーの意見を求めているのでしょう。しかし、仮にメンバーが勇気を出して、Bさんの考えとは異なる意見を述べたとします。
その時、Bさんは心から「なるほど、面白い視点だね!」と受け止められるでしょうか。
もしBさん自身の中に、判断への揺らぎや不安があれば、メンバーからの異論は有益な情報としてではなく、自分への批判や権威への挑戦として響いてしまうかもしれません。その無意識の動揺は、ほんの些細な表情の曇りや、わずかに守りに入った声のトーンとして表れます。
メンバーはそのサインを敏感に察知し、「ああ、やはり言わない方がよかったんだ」と学習し、次第に口を閉ざすようになります。Bさんは意図せずして、自ら意見の出ない状況を作り出してしまっているのです。
管理職にまず求められるのは、自分と異なる意見に晒されても、自身が揺らがないだけの健全な自信です。その自信があるからこそ、異論を攻撃ではなく別の視点として受け止め、チームの力に変えることができます。
メンバーに求められる「結果を受け入れる自信」
一方で、責任は管理職だけにあるのではありません。メンバー側にも、同様に健全な自信が必要です。
意見を言うということは、それが採用されない可能性も受け入れる、ということです。もし、勇気を出した意見が、議論の末に採用されなかったとしましょう。
健全な自信がなければ、意見が否定されたことを、まるで人格まで否定されたかのように結びつけてしまいがちです。「やっぱり自分の意見なんて価値がないんだ」と、次から挑戦する意欲を失ってしまいます。
しかし、健全な自信があれば、たとえ自分の意見が通らなくても、「今回は採用されなかったが、議論のプロセスには貢献できた」「決定した方針が最善であるよう、次は自分の力を尽くそう」と、適切に結果を受け止め、前を向くことができます。
意見が通らなかったときに、それを受け止め、組織の決定に従い次に向かえる思考と心。これもまた、プロフェッショナルとして不可欠な自信の一つの形なのです。
「静かな職場」を変える、はじめの一歩
冒頭のAさんとBさんのすれ違いは、この双方の自信が欠如していることから生み出された、組織の悲劇と言えるかもしれません。
「どうせ聞いてもらえない」というメンバーの不信感と、「どうせ言ってもらえない」という管理職の不満。この負のループを断ち切るには、どちらか一方の努力だけでは不十分です。
管理職は、まず自らの自信を問い直し、異論を歓迎できるだけの器を育む努力を。 メンバーは、意見を言う勇気と、その結果を真摯に受け止める強さを持つ努力を。
もちろん、これは言うほど簡単なことではありません。しかし、この健全な自信という土台なくして、本当の意味で活発な議論が生まれる組織風土は作れないのです。
真の生産的な双方向の議論は、充実した心理的資本がある組織にこそ生まれるものなのかもしれません。組織の心理的資本を高める方法については、こちらの講座で学んでいただくことができます。

PsyCap Master®(心理的資本開発指導士)として、やりとげる自信を高めるスキルを習得しませんか?PsyCap Master認定講座では、8週間のオンラインプログラムを通じて、やりとげる自信を高め、自律的な目標達成を促すコミュニケーション手法「ガイディング」を習得します。ガイディングは、経営学でエビデンスのある心理的資本の開発理論に基づいているため、確かな効果が期待できます。組織のリーダー、社内コミュニケーション開発担当の方/コンサルティング業/コーチ・カウンセラー業の方に必見のスキルです。