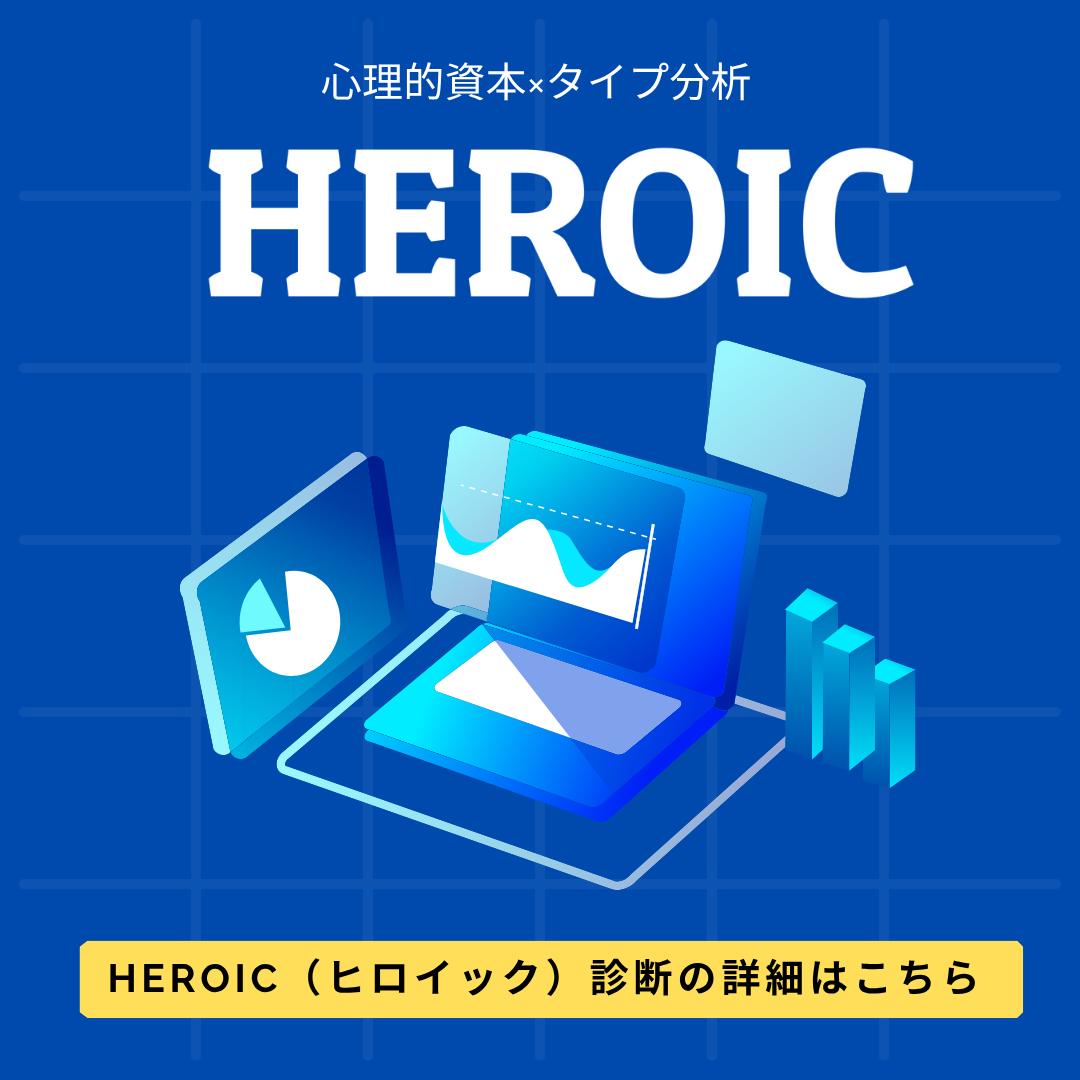「メンバーのモチベーションをどう引き出すか」
これは、多くの管理職が日々向き合っている普遍的な課題です。目標設定、1on1ミーティング、コーチング…。
様々な手法を試しても、相手によって手応えが異なり、「何が正解なのか」と悩む場面は少なくないでしょう。
特に「やる気」という言葉は曖昧で、メンバーのパフォーマンスが上がらない時、ついその一言で片付けてしまいがちです。しかし、その背景には、もっと複雑な要因が隠れているのではないでしょうか。
本稿では、メンバー一人ひとりの感情や個性という「変数」に過度に影響されず、より本質的で安定した関わり方を可能にするためのフレームワークとして、「心理的資本(Psychological Capital)」、通称「PsyCap(サイキャップ)」について解説します。
Contents
1. モチベーションの構造とマネジメントの難しさ
そもそも、人が行動を起こし、それを維持するための心理的エネルギーは「動機づけ(モチベーション)」と呼ばれます。これには、仕事そのものへの興味や成長実感からくる「内発的動機づけ」と、報酬や評価といった外部要因による「外発的動機づけ」があります。
これらの動機づけは、様々な要因によって変動します。
- 目標の適切さ:目標が高すぎても低すぎても、モチベーションには繋がりません。
- 周囲の環境:フィードバックの内容や、チーム内の人間関係も大きく影響します。
- 仕事への意味づけ:興味の持てない業務に、いかにして意義を見出すか。
- 自己効力感:「自分ならできる」という感覚がなければ、挑戦する意欲は湧きません。
- 心身の状態:プライベートな問題や体調も、パフォーマンスと無関係ではありません。
これらの要因は複雑に絡み合い、個人差も大きい。だからこそ、画一的なアプローチでは限界があり、マネジメントは難しいのです。
2. なぜ認識のズレは起きるのか?「個性」という変数
多くの管理職が、試行錯誤の末に「個性の違い」という壁に突き当たります。ロジカルで冷静な人もいれば、感受性豊かで共感を大切にする人もいる。このタイプの違いが、意図せぬコミュニケーションのズレを生むことがあります。
【ケーススタディ:ある1on1での出来事】
事実ベースで話を進めるタイプのリーダーが、プロセスや共感を重視するメンバーBさんと、困難なプロジェクトを終えた後の1on1を行いました。
リーダー:「Bさん、プロジェクトお疲れ様。最後までよくやり遂げてくれた。特に、クライアントに提出したデータ分析の精度は素晴らしかった。あの資料のおかげで契約に至ったよ。ありがとう」
Bさん:「…ありがとうございます。でも、本当に、大変だったんです。途中で何度も心が折れそうになって…」
この時、二人の間には認識のズレが生じていました。
リーダーは、具体的な成果を挙げて感謝を伝えたつもりでした。しかし、Bさんの反応は少し曇りがちに見えます。

リーダーは「What(何をしたか)」という成果を評価したのに対し、Bさんは「How(いかにして乗り越えたか)」というプロセスへの理解や共感を求めていたのです。
このような小さなズレが積み重なると、メンバーは「自分は理解されていない」と感じ、エンゲージメントを失いかねません。かといって、リーダーが全てのメンバーの感情の機微を読み取り、完璧に対応し続けるのは非現実的です。
そこで有効なのが、個々の感情の波に都度対応するのではなく、誰もが持つべきポジティブな心理状態、その土台そのものに働きかけるアプローチです。それが「心理的資本」です。
3. 解決策としての心理的資本(PsyCap)
心理的資本とは、経営学者フレッド・ルーサンス氏らによって提唱された概念で、「目標達成に向けて人の成長やポジティブなパフォーマンスを可能にする、ポジティブな心理的状態」と定義されます。
重要なのは、これが「性格」とは異なり、誰もがトレーニングや適切な関わりによって開発・強化できる「資本」であるという点です。
心理的資本は、4つの要素から構成されています。それぞれの頭文字をとり「HERO」 と呼ばれます。
- Hope(ホープ/意志と経路の力)
単なる願望ではなく、目標達成への強い意志(Will)と、そこへ至るための具体的な道筋を見出す力(Way)の両方を指します。困難に直面しても、諦めずに別の方法を探せる状態です。「自分ならこの仕事をやり遂げられる」と信じられる力です。これは、過去の「達成経験」、他者の成功を見る「代理経験」、周囲からの「言語的説得」、そして良好な「心身の状態」によって育まれます。
-
Efficacy(エフィカシー/自信と信頼の力)
「自分ならこの仕事をやり遂げられる」と信じられる力です。これは、過去の「達成経験」、他者の成功を見る「代理経験」、周囲からの「言語的説得」、そして良好な「心身の状態」によって育まれます。 -
Resilience(レジリエンス/乗り越える力)
逆境や困難な状況から立ち直り、その経験から学んで次へと進む力です。「心のしなやかさ」とも言え、失敗を引きずらず、未来の成功の糧とする姿勢を指します。 -
Optimism(オプティミズム/柔軟な楽観力)
物事のポジティブな側面に目を向け、成功を信じる現実的な姿勢です。成功は自分の力、失敗は一時的な外的要因と捉えることで、困難な状況でも挑戦を続けるエネルギーを維持します。これら4つの「HERO」は相互に影響し合い、高め合います。この心理的資本という土台を育むことが、個人の特性に左右されにくい、安定したマネジメントの鍵となります。
4. 【実践編】メンバーの心理的資本を高めるマネジメント・関わり方
心理的資本は、日々のコミュニケーション、特に1on1のような対話の場で育むことができます。ここでは、そのヒントとなる「対話例」をいくつか紹介します。
Hopeを高めるための対話例
- 「このプロジェクトの理想的なゴールを、君自身の言葉で描いてみてくれる?」
- 「そのゴールに向けて、私たちがまず踏み出すべき『最初の一歩』は何だろう?」
- 「もし計画通りに進まなかった場合、どんな代替案が考えられるかな?」
Efficacyを高めるための対話例
- 「以前、あの難しい課題をクリアした時、どんな工夫をしたか覚えている?あの時の君の行動は素晴らしかったよ。」
- 「今回の小さな成功を、次の挑戦にどう活かせそうかな?」
- 「少し難しい仕事だけど、君ならできると信じている。何かサポートが必要ならいつでも言ってほしい。」
Resilienceを高めるための対話例
- 「今回の経験から、私たちは何を学ぶことができただろう?」
- 「もし時間を戻せるとしたら、どの時点で違う判断をしただろうか。それはなぜ?」
- 「この悔しさを、次に進むエネルギーに変えるには、何ができるかな?」
Optimismを高めるための対話例
- 「この厳しい状況の中に、何か一つでもチャンスを見つけるとしたら何だろう?」
- 「今回の成功の要因は何だったと思う?君のどんな『強み』が活きたんだろう?」
- 「チーム全体がもっと前向きになるために、何かアイデアはある?」
大切なのは、これらの問いかけを通じて、メンバー自身が自分の内なる力に気づき、それを引き出す手助けをすることです。ただし、一方的な「問い詰め」にならないよう、普段からのポジティブなフィードバックで信頼関係を築いておくことが大前提です。
5. リーダー自身の心理的資本
最後に、リーダー自身の心理的資本の重要性について触れておきます。リーダー自身の心理状態が、チームの雰囲気やパフォーマンスに大きく影響することは、多くの研究で指摘されています。
リーダー自身が、
未来へのHopeを抱き、
自らの役割にEfficacyを感じ、
困難から立ち直るResilienceを持ち、
物事の明るい面を見るOptimismを失わないこと。
これらが満たされて初めて、リーダーの言葉や態度はメンバーにポジティブな影響を与えます。まずは自分自身の状態をセルフチェックし、必要であればケアすることも、リーダーの重要な役割の一つです。
まとめ
モチベーションに関する悩みは尽きないものですが、今回ご紹介した「心理的資本(PsyCap)」は、その悩みに新たな視点を与えてくれるフレームワークです。メンバーの感情に一喜一憂するのではなく、彼らが本来持つポジティブな心理状態の「土台づくり」に目を向ける。この考え方は、変化の多い今の時代、きっと多くの場面で役立つはずです。
この記事でお伝えできたのは、そのエッセンスに過ぎません。もし、この考え方について、より深く体系的に学びたいと感じられたなら、専門的なプログラムで学ぶという選択肢もあります。
例えば「PsyCap Master認定講座」では、理論的背景から実践的なスキルまでを習得することができます。マネジメントの「引き出し」を一つ増やす、という視点で検討してみてはいかがでしょうか。