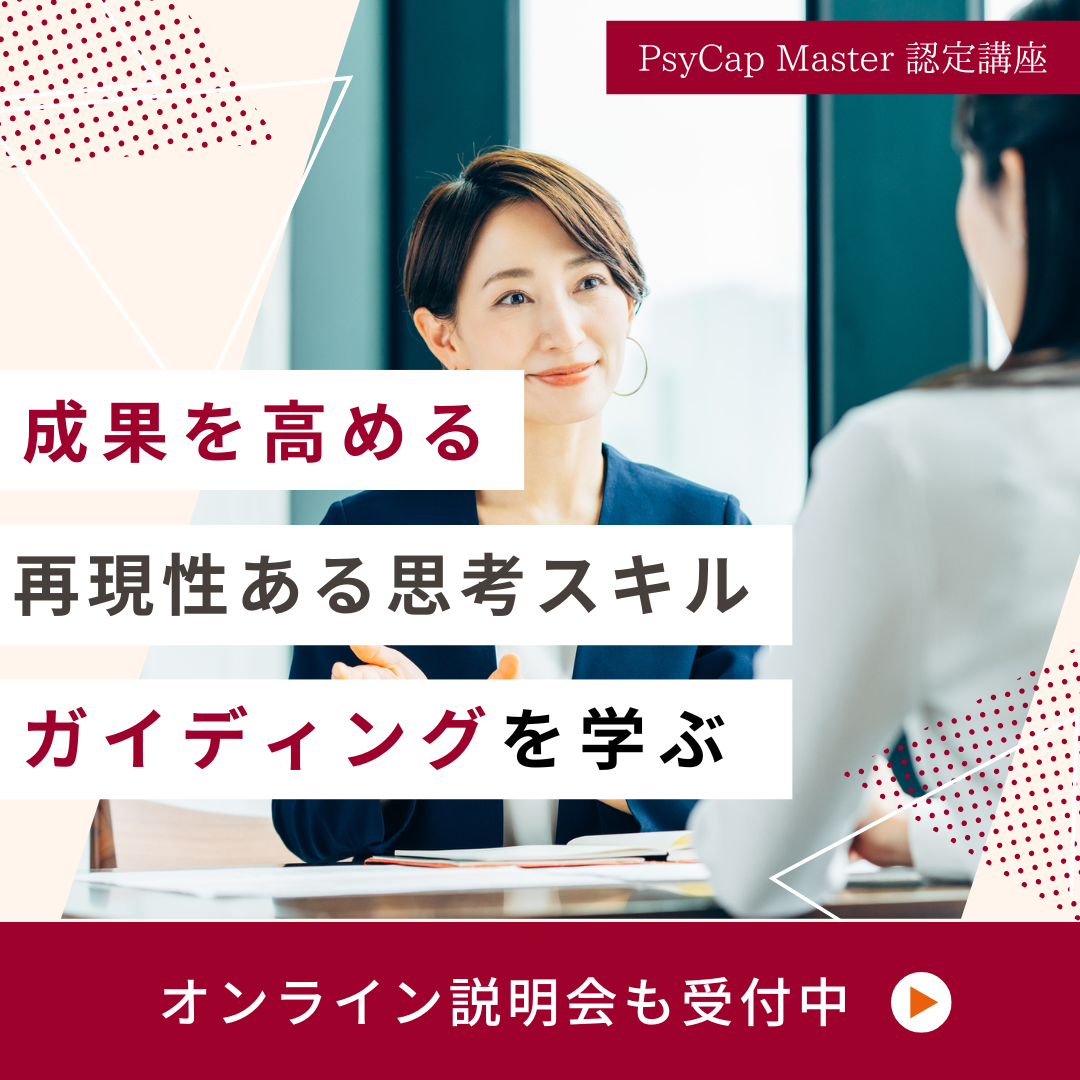Contents
意図を持った言動は相手の心に届かない
ゆとり世代として育った33歳の私ですが、最近、ある方が部下の動機づけについて話す中で、このような意見を述べておられました。
「ゆとり世代は『褒めてほしい』という姿勢が強かったので、褒めればよかった。でも最近のZ世代は、積極的に『褒めてほしい』とは言わない。そのくせ、褒めないとすねるんですよね」
なるほどそういうものかと思いつつも、私は何だか小さな違和感を覚えました。なぜか。後から気づいたのですが、それは「相手を誘導しようという意図が透けて見える」からではないかと思いました。褒める行為のその裏に、相手をある方向に導きたいという意図を感じたのです。
褒めることが、”本物の言葉・声”として相手の心に届いていない。これが部下を動機づけられていない本質の理由ではないだろうか。そう私は思いました。
飾りのない「頑張れよ」という言葉
昨年、祖父との電話でかけてくれた言葉が、私の心に深く残っています。祖父は私に「仕事の調子はどうか?」と聞いた後、最後に「頑張れよ」と声をかけてくれました。その言葉に私はとても勇気づけられ、その後も時々この言葉を思い出していたのですが、ふと「なぜこれほど心に残ったのだろう?」と疑問を持つようになりました。もちろん、肉親である祖父が言ってくれたという要素は多いにあるでしょう。それでも、文字にすると非常にシンプルな言葉です。
この疑問に対し私が持った仮説は、「何かに導こうという意図を含まない、飾りのない言葉だったから」ではないかということです。祖父自身が、孫である私に本当に頑張ってほしいという心から発した言葉だから、その思いが声のトーン・響きに乗り、それを私が受け取ったということなのかなと解釈しました。
本物の声ってなんだろう

「声は自分と他者を繋ぐもっとも身近にして最強のメディアです」「思いを伝え、人の心を動かし、自分自身を、そして将来をも変えていきます。」声の専門家である一般社団法人「声・脳・教育研究所」代表の山﨑広子さんは、著書の中でそう述べています。
私が偶然見たネット番組で山﨑さんが声について話されており、すぐに彼女の書籍を購入しました。番組を見たのは、ちょうど入院していた祖父の病状が悪化していた頃でした。頭はしっかりしているのに、言いたいことをスムーズに発声出来ない。一時的なものかと思っていましたが、さらなる病状と体力の低下とともに、ついに発声が困難になってしまいました。祖父の声を聞けなくなったとき、私の中で、「頑張れよ」と言ってくれた祖父の言葉から受け取ったエネルギーについて、もう一段掘り下げて考えたいと思ったのです。
「日本人女性の声は世界一高音」らしい
「日本人女性の声は世界一高音」と聞くと驚きませんか?山﨑さんによると、「様々な論文や私自身の実地調査を踏まえても、日本人女性のしゃべる声は、インドなどと並んで世界でも最も高い部類」なのだそうです。
その理由は、日本社会が求める「女性らしさ」に声の高さを合わせているから。無意識のうちに本来の地声よりも高い音を出しているのです。最近では社会の価値観の変化に伴い、若い男性も声が高くなっているそうです。
書籍では、このような高い声を作る現象を「クレーン女子」「クレーン男子」のように表現しています。まるでクレーンで背中を吊り上げられているかのように、心身に反して浮ついた声を発しているのだと指摘しています。
ちなみに、実を言うと私も、今の会社に転職した当初、今思えばこのクレーン男子でした。なぜかお客さんと話す時だけ、営業職特有のワントーン高い不自然な声になってしまい、自覚はあったのに直せなかったのです。皆さんの声はいかがでしょうか?
本物の自分の声(=オーセンティック・ヴォイス)でないと、相手に響かない
クレーンの例えとは対照的な、本物の声。これを書籍では「オーセンティック・ヴォイス」と表現しています。オーセンティック(authentic)とは、日本語で「本物の」「正真正銘の」「信頼できる」と訳されます。それは、その人の恒常性に合った声、心身が最も自然な状態で発する真実性のある声です。だからこそ、相手に伝わるのです。
書籍では、小学校低学年の担任を長年務めてきたY子さん(女性・30代)の事例が紹介されています。Y子さんは、学級崩壊の中で毎日「静かにしなさい!」「ちゃんと席について!」「先生の話を聞いて!」と叫び続けたため、声が何度も嗄れ、喉にポリープができてしまいました。病院で治療を受けましたが、再発を防ぐために声の出し方を変える必要がありました。Yさんの当初の希望は「ポリープを作らずにもっと大きな声を出せるようにしたい」でしたが、オーセンティック・ヴォイスのトレーニングを受けるうちに、なんと学級崩壊がぴたりと収まったのだそうです。
「声の表面的なストレスを取り去って、本来のもっともよい恒常性を取り戻した声、真実性のある声が出てきたとき、Y子先生が持っている本来の真面目さや優しさが子どもたちに伝わりました。」
書籍:8割の人は自分の声が嫌い 心に届く声、伝わる声 (P177)
本物の自分の声で褒めよう。相手に思いを伝えよう。
もしあなたが、組織のリーダーに限らず他者を動機づける立場であるならば、Y子さんのように、相手に伝わるオーセンティック・ヴォイスを活用したいと思いますよね。コラム冒頭で述べたように、Z世代を褒めるにしても、このオーセンティック・ヴォイスを使えば…
いや、ちょっと待ってください。何か重要なことを忘れていませんか?そうです。相手を意図的に誘導しようという下心からは、このオーセンティック・ヴォイスを発することはできないのです。相手(人間)は驚くほど敏感に、それを察知するのです。
「声を変える、良くする」という発想の裏を突き詰めていくと、誰しも「いかに自分を優位にするか」「いかに人を自分のもとに取り込むか」という目的が隠されていることがわかります。でも、それをよくよく考えていくと、その発想自体が自分の中に壁を作っていることに気がつきます。
書籍:8割の人は自分の声が嫌い 心に届く声、伝わる声( P212)
人間の聴覚は侮れないものです。生まれたときに備わっていた、すべての言語の発音を聴き取る能力には、オーセンティシティ(=真実性)への感受性も組み込まれています。(中略)オーセンティシティへの感受性は意識されないだけで、ずっと保持されています。
書籍:8割の人は自分の声が嫌い 心に届く声、伝わる声(P148)
書籍では、オーセンティック・ヴォイスの”見つけ方”についても具体的に言及されています。ぜひ書籍を手に取って頂ければと思います。
本物のリーダーシップ

ご紹介した書籍の内容とは違いますが、「オーセンティック・リーダーシップ」という言葉があります。これは、高い倫理観と自身の信念に基づき、自分らしさを発揮して組織やメンバーを導くという概念で、近年注目されているリーダーシップスタイルの一つです。きっと、オーセンティック・リーダーシップを発揮している人は、メンバーに対してオーセンティック・ヴォイスで接していることが容易に想像できます。
ネット・AI社会の今、「効果的な褒め方」「共感・理解を示す言葉」「思考を引き出す問い」などなど、様々なリーダーシップにおけるテクニックの情報が溢れています。しかし、それらを表面的に真似しても、相手の心には届かないかもしれません。”言葉”だけならAIでも発せられます。本コラムが本物の声・本物のリーダーシップについて考える一助になれば嬉しく思います。
私が祖父からかけてもらった声は、「オーセンティック・ヴォイス」だったのだと、書籍から理解することができました。私も、周囲の関わる人(仕事はもちろん、友人や家族)に対して、飾りのない「頑張れ」という言葉をかけられるような、オーセンティックな人間になれるよう、精進したいと思います。